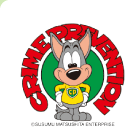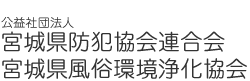- 宮城県防犯協会連合会
- 2018
七十七銀行原町支店において特殊詐欺被害防止キャンペーンを実施
仙台東地区防犯協会連合会では、傘下の原町防犯協会や警察署と連携し、年金支給日である4月13日(金)、七十七銀行原町支店において利用客を対象に特殊詐欺被害防止キャンペーンを実施しました。同キャンペーンは、防犯協会や警察官等10名が参加し、当日は、年金支給日でもあり、高齢者の利用客が多く、特殊詐欺の被害防止用チラシや防犯グッズを配布しながら、利用客一人一人に被害防止を呼びかけました。利用客からは「ご苦労様です、被害にあわないように気を付けます」などの声が寄せられるなど、有意義なキャンペーンとなりました。

宮城誠心短期大学における「セルフディフェンス講話」の実施
大崎東部防犯協会連合会では、警察と連携し、4月2日及び4月5日の2日間、大崎市に所在する「宮城誠心短期大学」において女子学生を対象に、女性を性犯罪等の被害から守るための「セルフディフェンス講話」を実施しました。「宮城誠心短期大学」は保育科が新設されたことに伴い、県北のみならず県内各地域や山形県等からの入学も増え、一人暮らしを始める女子学生が多くなっていることから、同短大の新学期オリエンテーションの機会を捉え、2日間に分けて1・2年生の女子学生を対象に、性犯罪の被害防止に向けた「セルフディフェンス講話」を実施したものです。
講話では、パワーポイントを使用し「性犯罪の発生状況、被害防止方策」、「ストーカー、デートDV、リベンジポルノからの守り方」、「電子マネー悪用の特殊詐欺の被害防止」等について、注意を呼びかけました。受講した学生からは「性犯罪やストーカーの怖さが分かりました、一寸したことに気を付けて被害を防ぎたい」などの声が聞かれ、学校関係者からは「大変好評で、来年も是非お願いしたい」との声が寄せられました。 

河北地区における「春うらら復興わかめ作戦」の実施
河北地区防犯協会では、警察や石巻市河北・雄勝・北上総合支所、交通安全協会等と協働で、4月6日(金)、道の駅「上品の郷」において、各種犯罪や交通事故防止を呼びかけるキャンペーンを実施しました。キャンペーンは「春うらら復興わかめ作戦」と銘打ち、防犯協会や総合支所職員、交通安全協会等約30名が参加、道の駅利用客等約300名に対し、特産のわかめと広報用「チラシ」等を配布しながら、特殊詐欺被害防止や、インターネットの安全利用、交通事故防止等を呼びかけました。利用客からは、「地域性のあるキャンペーンですね、被害にあわないように気を付けます」などの声が聞かれ、有意義なキャンペーンとなりました。

登米町わらすこかたり隊等によるあいさつ運動の実施
登米地区防犯協会連合会では、警察や「登米町わらすこかたり隊」と連携し、4月10日(火)、登米小学校児童約200名を対象に、防犯や交通安全を呼びかけるキャンペーンを実施しました。
「登米町わらすこかたり隊」は、平成16年に登米町老人クラブ連合会員を中心に設立された自主防犯ボランティア団体であり、地域の子供達の見守り活動を積極的に実施しています。同キャンペーンには、「登米町わらすこかたり隊」等約20名が参加し、新入学児童の初登校に合わせ、朝のあいさつとともに「チラシ、クリアファイル、ポケットティッシュ」等を配布し、防犯や交通事故防止を呼びかけました。児童らは笑顔でグッズを受け取り、「事故にあわないように気を付けます。」と元気な声で応えていました。 

大崎市民病院において防犯研修会を実施
大崎東部地区防犯協会連合会では、古川警察署と連携し、3月12日(月)、大崎市民病院において、不審者が侵入した際の対応要領について「防犯研修会」を実施しました。研修会には、病院職員約80名が参加し、最初に、パワーポイントを使い病院内での犯罪の発生状況や不審者に対する一般的な対応要領等について説明しました。その後、実技として不審者役の警察官を刺す股を使用して制圧する訓練実施し、また、刺す股がない場合は身近なものを活用して不審者との距離を保ち対応するよう指導しました。 最後に、不審者や痴漢等に対応する手段として、小手返し等の護身術の訓練を実施しました。参加者からは、「現在のところ、問題は起きていないが、日頃からの備えや訓練の大切さが分かりました。」などの声が聞かれるなど、有意義な研修会となりました。

JA年金友の会清滝班において特殊詐欺被害防止講話を実施
大崎東部地区防犯協会連合会では、古川警察署生活安全課と連携し、3月12日(月)、清滝地区公民館において、JA古川年金友の会会員70名を対象に、特殊詐欺被害防止講話を実施しました。JA古川年金友の会北部支部では各地区の会員を対象に健康講話等を実施していますが、今回、清滝班において、「特殊詐欺被害防止」を題材として講話を実施したいとの要望があり、警察署生活安全課員を講師として実施したものです。講話では、特殊詐欺の被害発生状況や一般的な手口等について説明した後、「きずなまち物語」のDVDを視聴し、その後、古川警察署管内の特徴点を基に被害防止対策について説明し、被害防止を呼びかけました。受講者からは、「我々や周りの人たちが被害にあわないように、今日受けた話しをみんなに伝えたい」等の声が寄せられました。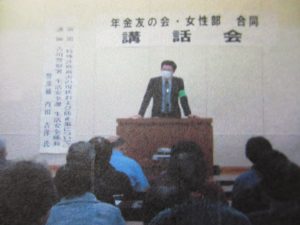

薬物乱用防止用広報資機材の「受渡式」を開催
宮城県防犯協会連合会では、3月19日(月)、県警察本部会議室において、県防連と県警察により薬物乱用防止用資機材の「受渡式」を開催しました。式には、県防連からは姉歯会長以下3名、県警察からは、小野寺組織犯罪対策局長以下10名が出席し、銃器薬物対策課次長から本受渡式開催の経緯について説明があり、引き続き、県防連会長と組対局長の挨拶の後、県防連会長から組対局長に対し、のぼり旗等の広報資機材を手渡しました。県内の薬物情勢は、平成29年中に県内で薬物事犯により検挙された人員は、前年と比較して20%増加するなど、宮城県内においても薬物乱用問題は極めて深刻な状況にあり、さらに、最近は、若者を中心に安易な気持で薬物事犯を起こす傾向があり、今後、インターネット利用による薬物乱用の拡散も懸念される状況にあります。このような薬物乱用問題は国の存亡を脅かす重大な問題であることから、当県防連では、薬物乱用防止用広報資機材として「横断幕・のぼり旗、チラシ等」を作成し、これら資機材を有効活用しながら、官民一体となって、広く県民に「薬物の恐ろしさ」について広報啓発し、「薬物乱用を根絶する社会環境づくり」を推進していくこととしています。


仙南ブロック「ホットスポットパトロール実践塾」の開催
宮城県防犯協会連合会では県警察と共催で、3月7日(水)、大河原町「えずこホール」において、仙南ブロックの地区防連会員や防犯指導隊員等を対象に「ホットスポットパトロール実践塾」を開催しました。 同実践塾は、仙南各地区防連防犯指導隊員や県防連、警察関係者、また、遠くは大崎西部地区や仙台北地区防連の関係者等約100名の出席の下に開催しました。実践塾では、犯罪社会学・警備保障論を専門とされている「仙台大学体育学部 田中 智仁準教授」を講師に招き、「日常に潜む犯罪の危険 ~街・家族・そして自分を守るために~」と題して、仙南各地区内の危険地域を写真で取上げ、危険箇所(ホットスポット)の選定、着眼点、パトロ-ルの実施方法等を個々具体的に講義を受けました。本実践塾は、今回初めての開催で、侵入犯罪や子ども女性の性犯罪等の被害防止に向けての基本的な活動である防犯パトロールのレベルアップを図ることを目的とし、開催したものです。当県防連と県警察では、今後とも県内各ブロック毎に本実践塾を開催することとしていますので、多数の方々の出席をお願いします。


三本木福祉のつどいにおける特殊詐欺被害防止講話の実施
大崎東部地区防犯協会連合会では、警察署と連携し、2月24日(土)大崎三本木総合支所において大崎市社会福祉協議会三本木支所が開催した「三本木福祉のつどい」において特殊詐欺被害防止講話を実施しました。同つどいは、三本木地区の高齢者を対象として、園芸品展示や舞踏民謡の発表などが行われるもので、参加した高齢者を対象に特殊詐欺の被害防止を呼びかけたものです。講話は、参加した高齢者約200名に対し、前半は、生活安全課員による還付金詐欺を題材とした寸劇を行い、後半は、生活安全課長による講話を実施し、管内における被害状況等を説明した後、「皆さんも方言を使って被害を防ぎましょう」などと、方言による被害防止を呼びかけました。講話終了後は、大崎東部地区防犯協会連合会長の呼び掛けで、参加者による「特殊詐欺だまされねっちゃ宣言」を行い、参加者一同で特殊詐欺被害撲滅を誓い合いました。

登米地区防犯協会で小・中学生に防犯グッズを贈呈
登米地区防犯協会連合会では、2月23日(金)、登米地区防犯協会が中心となり、登米小学校と登米中学校全校児童生徒330人に対し、防犯グッズ等を贈呈しました。防犯グッズの贈呈は、登米地区防犯協会が毎年行っているもので、当日は、防犯協会長や警察署員等が登米小学校を訪れ、校長室において代表児童2名に対し、「事件事故にあわないよう安全に気を付けながら、しっかりと勉強して下さい。」と言葉をかけ、「防犯ブザー」や「いかのおすしホイッスル」、インターネット安全利用標語「じょいふるクリアファイル」等を手渡しました。受け取った児童は、大きな声でお礼を述べ、「事件事故に巻き込まれないように気を付けて生活します。」と話すなど、児童生徒に対する防犯意識の高揚につながったものと確信しました。